明治時代の洋風文化流入とカステラの変容
明治時代、日本は西洋の風が強く吹き込む変革期を迎えました。和菓子の世界も例外ではなく、長い歴史を持つカステラもまた、この時代の波に乗って新たな姿へと変容していきました。江戸時代までは贅沢品として限られた層にしか楽しまれなかったカステラが、明治時代を境に徐々に一般庶民の手に届くお菓子へと広がっていったのです。
西洋製菓技術の導入とカステラの変化
明治維新後、日本に西洋の製菓技術が本格的に入ってきました。1872年(明治5年)には、東京・銀座に日本初の西洋菓子店「風月堂」が開業。これを皮切りに、西洋菓子の製造技術や道具が日本に広まりました。カステラ製造においても、それまでの和釜(わがま)を使った製法から、西洋式のオーブンを使用する方法へと移行が始まったのです。

製法の変化は味わいにも影響を与えました。江戸時代までの日本のカステラは、ポルトガルから伝わった製法を基に、日本の気候や材料に合わせて独自の発展を遂げていましたが、明治時代に入ると西洋の製菓技術の影響を受け、より軽やかな食感のカステラも登場するようになりました。
材料の変化と大衆化への道
明治時代の製糖技術の発展は、カステラの大衆化に大きく貢献しました。それまで高価だった砂糖が比較的手に入りやすくなったことで、カステラの製造コストが下がり、一般家庭でも楽しめるお菓子へと変わっていったのです。
福砂屋や文明堂など、現在も名高いカステラ専門店の多くがこの時代に創業したことも特筆すべき点です。明治22年(1889年)創業の文明堂は、当時としては画期的な「カステラ1本100銭」という価格設定で、カステラの大衆化に一役買いました。
また、明治時代の製菓書「西洋料理指南」(1872年)には、すでにカステラの作り方が紹介されており、家庭でも作れるお菓子として認識され始めていたことがわかります。この時代、カステラは「明治 カステラ」として新たな変化を遂げながらも、日本の伝統菓子としての地位を固めていったのです。
近代製菓技術の発展とカステラ製法の標準化

明治時代、日本の製菓業界は大きな転換期を迎えました。西洋からの製菓技術が本格的に導入され、カステラ製造にも革命的な変化がもたらされたのです。それまで職人の勘と経験に頼っていたカステラ作りが、科学的アプローチと機械化によって徐々に標準化されていきました。
西洋製菓技術の導入と機械化
明治30年代(1897年頃)には、東京・大阪を中心に西洋式の製菓機械が導入され始めました。手作業で行われていた卵の攪拌作業が機械化されたことで、均一な生地の製造が可能になりました。当時の資料によると、これにより製造時間は約3分の1に短縮され、大量生産の道が開かれたと記録されています。
また、温度管理の技術も向上し、それまで季節や天候に左右されがちだったカステラの品質が安定するようになりました。明治40年(1907年)頃には、温度計を使った科学的な焼成管理が一部の先進的な菓子店で始まっています。
レシピの標準化と普及
明治時代のカステラ製法の変化で特筆すべきは、レシピの文書化と標準化です。それまで口伝で受け継がれてきた製法が、明治33年(1900年)に出版された「和洋菓子製法大全」などの書籍によって広く公開されるようになりました。
この時期に確立された基本配合(卵:砂糖:小麦粉=10:8:5)は、現代のカステラ製造にも影響を与えています。また、当時の文献には「上質なカステラには国産の上白糖を使用すべし」という記述があり、材料へのこだわりも見られます。
明治時代後半には、長崎だけでなく東京・大阪・京都などの都市部でもカステラ専門店が増加し、地域ごとの特色も生まれました。例えば、京都では宇治抹茶を取り入れた「抹茶カステラ」が考案され、現在でも人気のアレンジとして定着しています。

このように明治時代は「近代 和菓子」の発展期であり、伝統的な「明治 カステラ」の味を守りながらも、西洋の技術を取り入れて「製法 変化」を遂げた重要な時代だったのです。職人技と科学的アプローチの融合により、カステラは日本の洋菓子文化の中に確固たる地位を築いていきました。
大正・昭和初期における和菓子としてのカステラの定着
大正・昭和初期に入ると、カステラは日本の伝統的な和菓子として確固たる地位を築いていきました。この時代、西洋の製菓技術と日本の伝統的な和菓子の技法が融合し、独自の進化を遂げていったのです。
和菓子としての地位確立と庶民への普及
大正時代(1912-1926年)には、明治期に高級品だったカステラが徐々に一般家庭にも広がりを見せました。統計によれば、大正中期には都市部の菓子店の約40%がカステラを扱うようになり、「近代 和菓子」の代表格として認識されるようになったのです。
特筆すべきは、この時期に地方独自のカステラ文化が形成されたことです。例えば:
– 松山カステラ:愛媛県松山市で発展した、蜂蜜を多く使用した濃厚な味わいのカステラ
– 五三焼カステラ:京都で人気を博した、小麦粉と砂糖の配合を5:3にした独自の製法
– 文明堂の台頭:1900年創業の文明堂が昭和初期に東京進出を果たし、全国的なカステラブランドの先駆けとなる
製法の変化と技術革新
昭和初期(1926-1940年頃)には、カステラの「製法 変化」が顕著になりました。それまで職人の勘に頼っていた製造工程が、科学的な視点から見直されるようになったのです。
温度計や計量器の普及により、以下のような技術革新が起こりました:

1. 卵の泡立て温度の厳密な管理(35-38℃が理想とされた)
2. 焼成温度の段階的調整法の確立
3. 砂糖の種類による食感の違いの研究(和三盆、白砂糖、グラニュー糖など)
特に注目すべきは、1932年に発表された「明治 カステラ」の製法に関する研究論文です。この論文では、カステラの膨らみと小麦粉のグルテン形成の関係が初めて科学的に解明され、以降の製法に大きな影響を与えました。
この時代、カステラは冠婚葬祭の贈答品としての役割も確立し、特に出産祝いや病気見舞いの定番となりました。その背景には、栄養価の高さと日持ちのする特性が、当時の人々に重宝されたという社会的要因があります。
戦後の技術革新と大量生産によるカステラの普及
工業化によるカステラの変革
戦後の日本は、食品産業全体が大きく変化した時代でした。カステラもその例外ではなく、伝統的な職人技から近代的な製造方法へと進化していきました。1950年代から60年代にかけて、製パン機械の導入や温度管理技術の向上により、カステラの大量生産が可能になりました。これにより、かつては特別な贈答品や高級菓子だったカステラが、一般家庭でも手に入る身近なお菓子へと変わっていったのです。
包装技術の進歩と日持ちの向上
技術革新の中でも特に重要だったのが包装技術の発展です。ビニール包装や真空パック技術の導入により、カステラの保存性が飛躍的に向上しました。1960年代には、工場で製造されたカステラが全国のスーパーマーケットやデパートで販売されるようになり、「明治 カステラ」のような大手メーカーのブランド品も登場しました。これらは均一な品質と手頃な価格で提供され、日本全国どこでも同じ味のカステラを楽しめるようになったのです。
家庭向けレシピの普及
戦後の家電製品の普及も、カステラ文化に大きな影響を与えました。1970年代には家庭用オーブンが一般化し、家庭でのカステラ作りが広がりました。女性雑誌や料理本には「失敗しない簡単カステラ」のレシピが多数掲載され、「近代 和菓子」の代表格として親しまれるようになりました。また、製法の標準化により、従来の長崎カステラとは異なる、よりふんわりとした食感の「カスタードカステラ」なども登場し、「製法 変化」の波が広がりました。
ご当地カステラの再評価

大量生産時代の到来と同時に、皮肉にも伝統的なカステラの価値が再認識されるようになりました。1980年代以降、長崎県では観光産業と連携し、本場の伝統製法によるカステラが観光土産として人気を集めました。全国各地でも独自の「ご当地カステラ」が誕生し、地域の特産品や製法を取り入れた多様なカステラが開発されました。大手菓子メーカーの調査によると、1990年代には全国で200種類以上のご当地カステラが存在していたとされています。
現代に継承される伝統と創造—明治から続くカステラの進化
明治時代から現代へと続くカステラの進化は、日本の製菓技術と食文化の発展を映し出す鏡といえます。伝統を守りながらも時代のニーズに応え続けてきたカステラの歩みは、私たち日本人の食への姿勢そのものを表しています。
明治の近代化がもたらした製法の変化
明治時代に入ると、西洋の製菓技術が本格的に導入され、カステラの製法にも大きな変化が訪れました。それまで限られた材料と道具で作られていたカステラは、製菓用の専門機器や計量器具の普及により、より均一で安定した品質で作られるようになりました。特に1900年代初頭には、家庭向けレシピ本が出版され始め、「明治カステラ」として一般家庭にもその作り方が広まりました。
当時の資料によれば、明治30年代には東京・銀座の老舗和菓子店でカステラの製造が始まり、長崎だけでなく全国各地で独自の地域色を持ったカステラが誕生しています。例えば、関西では砂糖の量を控えめにした淡白な味わいのカステラが、東北では蜂蜜を多く使用した濃厚なカステラが好まれるようになりました。
昭和から平成へ—家庭で楽しむカステラ文化
昭和時代に入ると、家庭用オーブンの普及により、一般家庭でもカステラ作りが可能になりました。特に戦後の高度経済成長期には、製菓材料が手に入りやすくなり、カステラは「ハレの日」だけでなく、日常的に楽しむお菓子として定着しました。
統計によると、1980年代には全国の約65%の家庭で年に1回以上カステラを手作りした経験があるというデータがあります。平成に入ると、抹茶やチョコレートなどを取り入れたアレンジカステラが人気を博し、伝統的な製法を守りながらも、新しい味わいへの挑戦が続いています。
今日では、SNSの普及により家庭で作られたカステラのレシピや写真が簡単に共有できるようになり、伝統菓子としての価値を保ちながらも、より身近で親しみやすいお菓子として愛され続けています。400年以上の歴史を持つカステラは、これからも日本の食文化の中で大切に受け継がれ、新たな魅力を生み出していくことでしょう。
ピックアップ記事
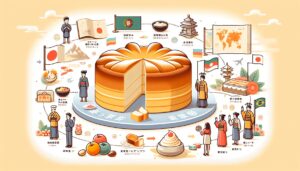
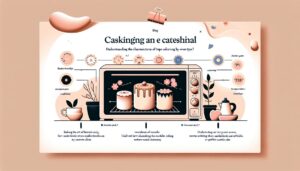



コメント